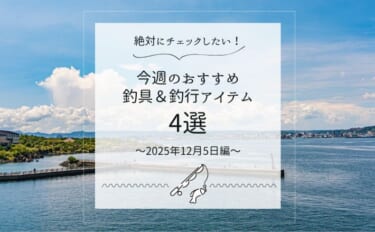シーバス釣りにおいてベイト(エサ)を知る事はとても重要だ。そこで今回は、シーバス釣りの基本とも言える「ベイト」の種類や生態について、主に河川での釣りを中心に解説したい。
(アイキャッチ画像提供:TSURINEWSライター宮坂剛志)
各ベイトによる狙い方
ベイトの種類や生態がわかった所で、次はその各ベイトを捕食しているシーバスをどう狙ったらいいか?について解説したい。
ボラ(ハク、イナッコ)
 ハク(提供:TSURINEWSライター宮坂剛志)
ハク(提供:TSURINEWSライター宮坂剛志)春先の幼魚(ハク)は、主に浅い河川で群れになって見られる。よく見ると、岸際でピカピカ光っているのがわかる。遊泳力がそれほどないので、産卵後でまだ体力が戻りきっていないシーバスにはありがたいベイトだ。しかも大量にいるので、このハクに付いたシーバスは驚くほど貪欲だ。
このハク着きのシーバスを釣るのはベテランでも難しい。大きな群れにシーバスの意識が集中しており、小さなルアーには意識がなかなか向かないからだ。
攻略法は様々だが、一番簡単なのはメバル用などの小さいルアーをキビキビ動かすことだ。
いっぽう、夏~秋にかけてのボラ(イナッコ)は、ハクと違い、やや大きめのルアー(8~12cm)を使う。ブラックバス用のシャッド系のルアーなどがピッタリだ。こちらもイナッコが大量にいると、ルアーへの反応は薄い。これを攻略するには、ブルブルと速く動かすハデなアクションが効果的だ。
ハゼ
 バイブレーションにヒットしたハゼ(提供:TSURINEWSライター宮坂剛志)
バイブレーションにヒットしたハゼ(提供:TSURINEWSライター宮坂剛志)ハゼ着きのシーバスには、バイブレーションがおすすめだ。しかも小型(5~8g)のものがいい。ハゼは底(ボトム)付近にいるので、これを狙うシーバスもボトムを見ている。狙いは初夏から晩秋の、最もハゼのサイズがよくなる季節だ。
ボトムにバイブレーションを当てながらズルズル引いてくるイメージをすると釣りやすい。外道でクロダイやマゴチ、また、ハゼそのものが釣れたりするから面白い。
カニ、エビ(甲殻類)
 バイブレーションでキャッチ(提供:TSURINEWSライター宮坂剛志)
バイブレーションでキャッチ(提供:TSURINEWSライター宮坂剛志)カニを食べているシーバスも、基本は底(ボトム)を見ている。こちらも初冬のエサが少なくなる季節が中心だが、実はシーバスは一年中カニを食べている。
カニはハゼと違い、けっこう素早い。バイブレーションでゴツゴツとボトムに当てながらやや速めに引いてくるといい。バイブレーションはやはり小型(5~8g)がいいが、着底のわかる重さを考えて選ぶといい。
エビは少し難しい。シンキングペンシルやバイブレーションなどでも釣れるが、実はエビに似せたワームの方がよかったりもする。エビに似せて飛び跳ねるように、ボトム付近でサオをシャクって誘う方法が有効だが、普通にバイブレーションでボトムを素早く引いて来るだけでも釣れたりする。
エビは春先のベイトが動きだす季節に捕食されるが、夏場でも食べられていたりする。
ポイントはルアーを素早く動かす所にあるが、実は一番難しいのは、エビは根掛かりの多い所に生息していることだ。カニもそうだが、アシ際やボトムにある障害物周りが好きだ。当然シーバスもベイトを狙って障害物周りに付くとなると、根掛かりのリスクは高くなるので難しいベイトと言える。
イソメ、ゴカイ
 バチパターンで攻略(提供:TSURINEWSライター宮坂剛志)
バチパターンで攻略(提供:TSURINEWSライター宮坂剛志)このベイトに付くシーバスを狙うには、やはり冬場のバチ抜けだろう。ベイトの生態の所でも紹介したが、バチ抜けとはイソメやゴカイの産卵行動だ。潮が大きく動く大潮がいいと思われがちだが、実はその前後の中潮などが釣りやすい。バチ抜けの基本は、細身の動かないルアーを使うことが基本だが、風がないのなら小さなワームでもいい。
このバチ抜けを待っているシーバスは、冬の寒い時期で元気(活性)がない。よって、あまり動き回ってエサを捕食しない。それを考えて、ルアーもアクションは付けない。川の流れを利用して、ナチュラルに流れてくるイソメやゴカイを演出することがポイントだ。
風などが吹いた場合、水面にイソメやゴカイが浮かない場合があるが、底(ボトム)を流れている場合があるので、ゆっくり沈むルアー(シンキングペンシル)か、重めのジグヘッドにワームを使うといい。
ベイトは超重要な要素
いかがだっただろうか?簡単ではあるがシーバス釣りにおいての原点、「ベイト」について書いてみたが、ベイトについてはまだまだ未知な部分が多く、これだと言う正解もない。
例えば、ベイトの形や大きさにルアーを合わせる”マッチザベイト”というルアーセレクト方法があるが、これも絶対ではない。ボロボロで色が剥げた壊れかけのルアーで爆釣!なんてこともある。だからこそ奥が深いシーバス釣りは面白い。
しかし、シーバス釣りにおいてベイトは超がつくほど重要な要素であることは間違いない。ベイト一つで釣果がガラリとかわることなんて普通にある。
シーバス釣りにオフシーズンはない。一年中釣れるターゲットだ。そのシーバスを確実に手にしたいのなら、やはりベイトの研究はかかせない。ぜひ、ベイトを極めてよりよい1匹に出会えるように釣行を重ねてほしい。
<宮坂剛志/TSURINEWSライター>