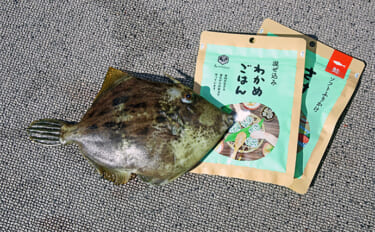海釣りを気軽に楽しめる海上釣り堀。メインターゲットとして釣れるのは、魚の王様と言われるマダイや青物だ。せっかく釣り堀に行くのであれば、1匹でも多く釣りたい。そこで今回は、海上釣り堀で釣果を上げる仕掛けセットや竿、エサについて解説。数を多く釣るためのポイントも紹介していく。
(アイキャッチ画像提供:週刊つりニュース関東版APC・間宮 隆)
海上釣り堀とは?
海上釣り堀は、海の上に作られた釣り堀のこと。豊富な魚種をイケスの中に放流しており、海の釣りを気軽に楽しめることで人気のスポットだ。
エサ釣りが基本で、ウキの反応を見るウキ釣りかラインの変化を感じ取るミャク釣りで狙っていく。ルアーで魚を狙うことは禁止されている場所が多い。
料金体系は、釣った魚を定額で持ち帰れる「釣り放題方式」と釣った分だけ料金が上乗せされる「買い取り方式」の2種類。
みんなが釣りを楽しむために、海上釣り堀によって、ロッドの長さや本数、仕掛けにルールが定められている。初めての場所に訪れるときは、事前にルールを確認してから道具を用意していこう。
 海上釣り堀で釣れたマダイ(提供:週刊つりニュース関東版・坂本康年)
海上釣り堀で釣れたマダイ(提供:週刊つりニュース関東版・坂本康年)海上釣り堀で釣れる魚
海上釣り堀では、海に生息するさまざまな魚が釣れる。中でも目玉のターゲットは、高級魚であるマダイや、大きな魚体で強い引きを見せるブリ、カンパチ、ヒラマサなどの青物だ。
マダイは手ごろなサイズが数多く放流されており、強い引きを感じられる。ファミリーで釣りを楽しむことも可能だ。
イケスを走り回る青物は、掛けた釣り人がある程度海上釣り堀を動き回ってファイトしないと取り込めない。釣り人同士のオマツリ(糸が絡むトラブル)を防ぐため、誰かに青物がヒットしたら仕掛けを引き上げて取り込みに協力してあげよう。
 海上釣り堀で釣れた10kg級ヒラマサ(提供:週刊つりニュース中部版 桑原一幸)
海上釣り堀で釣れた10kg級ヒラマサ(提供:週刊つりニュース中部版 桑原一幸)海上釣り堀のタックル
海上釣り堀で使用するタックルは、マダイ・青物の両方を1タックルで狙う場合、3.5m前後の海上釣り堀専用ロッドか、またはオモリ負荷3号前後の磯竿に3000~4000番のスピニングリール。ラインはPEライン3号前後で、ウキ釣り仕掛けが一般的だ。
手軽に釣行できる海上釣り堀は1タックルで釣行するのもいいが、可能であればマダイ用、青物用とそれぞれ1セットずつ準備した方が、状況に応じた細かい対応が可能になる。また1本の竿にトラブルが起きた場合でも、もう1本の竿で釣りを継続することができることもあり、複数タックルを準備することをおすすめする。
 海上釣り堀でゲットしたマダイ(提供:週刊つりニュース中部版 桑原一幸)
海上釣り堀でゲットしたマダイ(提供:週刊つりニュース中部版 桑原一幸)