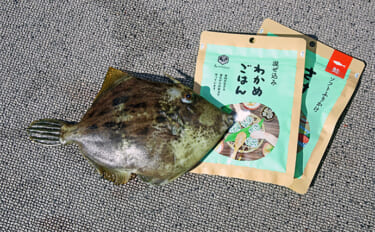ニジマスはサケ科の淡水魚で、英名は「レインボートラウト」。スーパーやお寿司屋さんでよく見る「トラウトサーモン」は、多くがこの海面養殖を行ったニジマスで、実は釣りをしない人にとっても身近な魚です。今回はそんなニジマスを美味しく食べるためのレシピを紹介。また、この魚を美味しく料理・保存するには水分を抜くことや臭み取りも重要になるので、食べ方以外にも下処理方法やさばき方、最適な保存方法なども徹底解説します。
(アイキャッチ画像提供:週刊つりニュース関東版APC・藤崎信也)
ニジマスの下処理
ニジマスは水分が多いため傷みやすく、餌などの生育環境によってどうしても臭みのあるニジマスが存在します。そのため、釣り上げた後の丁寧な下処理も美味しく食べる鍵となります。まずは、釣ったニジマスの下処理方法を紹介していきましょう。
血抜きと締め処理
ニジマスの場合、血抜きや締めは省略してしまう人も多いですが、しっかり血抜きと締め処理を行うことで臭みが減り、鮮度の保ちもよくなります。まずナイフなどで脳天を刺して脳締めを行い、エラを切ったらバケツやクーラーの水の中(氷冷水で行うのが魚体も冷やせてベスト)などでエラを持ちながら魚体を振り放血します。可能なら神経締めまで行うといいでしょう。
また、血抜き時には管理釣り場に血を流すのはNG。釣り場を汚さないように、必ずクーラーやバケツの中か、さばき台で行うようにします。1匹1匹締めるほうが魚にストレスを与えずおいしさは保たれますが、数釣りが当たり前のエリアトラウトでは中々面倒。キープする魚を活かしておいて、締め→血抜き→ヌメリ&ウロコ取りまで釣り場のさばき台で処理してしまうとスムーズでしょう。
ぬめり取り&ウロコ取り
たわしやステンレスたわしなどを使って魚体をゴシゴシこすると、ヌメリとウロコが一緒にとれます。水で流してヌメリがある程度なくなればOKです。この処理を行わないとまな板の上で魚が動いてしまい、さばきづらくなるほか、臭みの原因にもなります。
 ウロコをとり流水で洗い流す(提供:週刊つりニュース関東版 小谷)
ウロコをとり流水で洗い流す(提供:週刊つりニュース関東版 小谷)持ち帰るまでの保存
持ち帰るまでの保存の仕方は水に漬けておくのはNG。身が水を吸って美味しくなくなるほか、雑菌も繁殖しやすくなります。また、鮮度を落とさないよう保冷も必ず行いましょう。釣り場での下処理が終わったら、魚体から水気を拭き取り、袋などに入れ、氷を入れたクーラーボックス内で保存するといいでしょう。
ニジマスのさばき方
ヌメリ&ウロコが取れたらさばいていきましょう。包丁が苦手な場合は、ハサミでも代用できます。
頭を残す場合のさばき方
頭を残して串刺しにしたり、見栄え重視で料理する場合はこちらの方法でさばきましょう。
1.包丁をお尻から入れて下アゴの付け根まで刃を動かす。
 腹に刃を入れる(提供:週刊つりニュース関東版 小谷)
腹に刃を入れる(提供:週刊つりニュース関東版 小谷)2.エラと内臓を取る。
 エラを取る(提供:週刊つりニュース関東版 小谷)
エラを取る(提供:週刊つりニュース関東版 小谷)3.血合いに刃を入れて水できれいに洗い流す。
 血合いを綺麗に洗い落とす(提供:週刊つりニュース関東版 小谷)
血合いを綺麗に洗い落とす(提供:週刊つりニュース関東版 小谷)頭を落とす場合のさばき方
単純に身を使いたい場合はこちらのさばき方がオススメです。三枚おろしにする場合も頭は落としておきましょう。
1.胸ビレの後ろから包丁を入れて頭を落とす。
 頭を切り落とす(提供:週刊つりニュース関東版 小谷)
頭を切り落とす(提供:週刊つりニュース関東版 小谷)2.腹側からお尻まで包丁を入れる。
3.内臓を取り、血合いに刃を入れてきれいに流す工程は同じ。
三枚おろしのやり方
小型のニジマスを焼き物にする場合はそのまま丸ごと焼いてしまってもいいですが、大型の個体の焼き物や刺身にする場合などは三枚おろしまで行いましょう。
1.中骨に沿って頭側から包丁を入れ、コツコツと中骨に当たっているのを感じながら尾側へ動かす。反対側も同様に行う。
 三枚おろしにする(提供:週刊つりニュース関東版 小谷)
三枚おろしにする(提供:週刊つりニュース関東版 小谷)2.半身になったら腹骨を斜めに包丁を入れてすき取る。この際、最後は包丁の刃を立てて切る。
 腹骨を取る(提供:週刊つりニュース関東版 小谷)
腹骨を取る(提供:週刊つりニュース関東版 小谷)皮引きについて
刺身の場合や、皮が苦手な人は皮も引いていきます。端から包丁を立てて、皮を切らないように前後に振りながら動かしていきます。ニジマスの皮はとても柔らかいため、皮引きが苦手な人が多いかもしれません。その場合は端だけ包丁を入れて、後は手で剥くこともできます。
 皮を引く(提供:週刊つりニュース関東版 小谷)
皮を引く(提供:週刊つりニュース関東版 小谷)小骨(血合い骨)について
こちらも刺身で食べる場合や、小骨が苦手な人は取っていきましょう。小骨は三枚下ろしにした状態から指の触感と目視で位置を確認し、ていねいに1本1本毛抜きで小骨を抜いていきます。これはかなりの手間なので、どうしても面倒臭い人は、小骨部分を削いでしまうと簡単です。触れば大体の場所は把握できるので、そこの部分を思い切って切り取ると、身は少しもったいないですが、時短になります。
 毛抜き等で血合い骨を除こう(提供:週刊つりニュース関東版 小谷)
毛抜き等で血合い骨を除こう(提供:週刊つりニュース関東版 小谷)ニジマスの保存方法
すぐに食べずに保存する場合は腐敗の原因となるため、内臓を取って血合いを洗い、エラを取る工程まで行いましょう。水気をしっかり取ってから、ドリップを吸収するキッチンペーパーに包み、空気に触れないようラップでもしっかり包んでからジップロックなどに入れ保存します。冷蔵庫内ではなるべく低温のチルド室やパーシャル室で保存するといいでしょう。
冷凍保存する場合
冷凍保存する場合も水分を取ることと、なるべく空気に触れないようにすることが重要です。上記同様の処理でもいいですが、食品用脱水シートに包んだ上で空気に触れないように保存すると、冷凍・解凍時の身のダメージを抑えられるためオススメです。